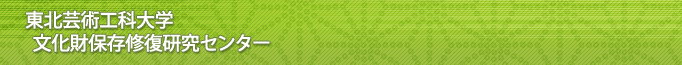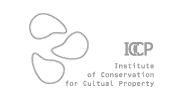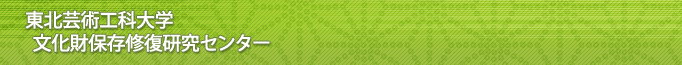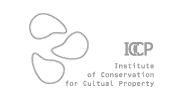大地震や台風等の自然災害や盗難等の人災により文化遺産は罹災し、傷つき、失われていく。最近は、列島各地で台風による水害や、震災、火災が相次ぎ、国宝や重文を始め多くの文化財が影響を受けている。10年前の阪神・淡路大震災でわれわれが学んだのは、「救うべきは、人も文化財も」であったが、この間防災の視点では、文化遺産への配慮が十分であったとはいい難い。地域の歴史的町並みや貴重な文化財が災害に見舞われることは、地域市民の精神的な支柱を喪失することに繋がり、また地域の活力を減らすことも招きかねない。行政や市民が、文化遺産に対しても危機管理意識を高め、防災対策を地域ごとに立てる必要があるし、不幸にして災害に遭遇した後は、速やかに地域が文化遺産を含めて復興できるような協力体制が不可欠である。
ここでは、様々な災害に対する予防的な保存対策や、災害が発生した場合の対応策について研究する。災害への予防的対策としては、文化遺産の公開による地域市民の意識喚起と地域の消防機関の指導による自主防災組織等の協力体制、未指定文化財の種別悉皆調査(保存状態・保存環境)による地域における文化遺産の所在地地図集成などが課題である。また災害時における対応策としては、文化遺産の救済活動を実践できる専門家の育成や人的ネットワークの構築が必要不可欠である。研究対象として、文化遺産を中核として形成された歴史都市、山形県鶴岡市を採り上げ、教育委員会や消防機関、致道博物館等文化財関連施設と連携・推進を模索する。
これらの研究と関連して、災害に強い文化財の収蔵環境・展示環境の開発研究もテーマとする。