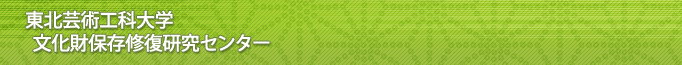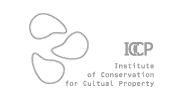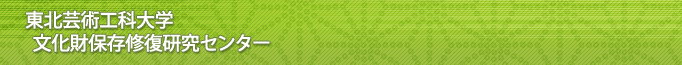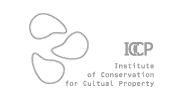|
 |
|
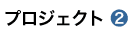 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
長坂一郎 |
文化財保存修復研究センター長・美術史・文化財保存修復学科(兼任)教授 |
地域文化遺産の再発見・再評価と保存・活用システム
研究課題鳥居に関連するアジア美術の学術調査・再評価 |
|
藤原 徹 |
文化財保存修復研究センター・美術史・文化財保存修復学科(兼任)教授 |
地域文化遺産の再発見・再評価と保存・活用システム
研究課題山形盆地に遺る石造鳥居群の保存状態調査・修復計画、最上川流域の雛人形の状態調査 |
|
半田正博 |
文化財保存修復研究センター・教授 |
地域文化遺産の再発見・再評価と保存・活用システム
研究課題東洋絵画・書蹟・古文書などの保存状態の調査 |
|
張 大石 |
文化財保存修復研究センター・准教授 |
地域文化遺産の再発見・再評価と保存・活用システム
研究課題プロジェクト・リーダー山形盆地に遺る石造鳥居群の保存状態調査・修復計画、不可動文化財(鳥居・窯跡・炉跡遺跡)の3D計測 |
|
岡本篤志 |
文化財保存修復研究センター・嘱託研究員 |
彫刻・工芸作品、石鳥居、石橋、建造物等の三次元計測とデジタルアーカイブ等
研究課題地域文化遺産の三次元計測技術等による保存・活用システム研究 |
|
内藤正敏 |
大学院・教授 |
地域文化遺産の映像による保存・活用システム
研究課題写真による文化遺産の地域還元 |
|
加藤 到 |
情報デザイン学科・准教授 |
地域文化遺産の映像による保存・活用システム
研究課題地域文化遺産の映像記録の作成と地域への還元 |
|
増澤文武 |
大学院・客員教授(NPO・日本文化財保存機構理事) |
地域文化遺産の再発見・再評価と保存・活用システム
研究課題石造鳥居の保存状態調査・修復施工計 |
|
 |
|
西浦忠輝 |
国士舘大学・教授 |
地域文化遺産の災害予防研究と持続的保存・活用
研究課題地域と地域文化遺産を災害から守る防災対策 |
|
尾立和則 |
|
地域文化遺産の災害対策研究と持続的保存・活用
研究課題被災歴史資料・文字資料への緊急対応 |
|
荻原秀三郎 |
民族学研究者 |
アジア信仰史的視点による鳥居についての考察
研究課題地域文化遺産のアジア信仰史的視点による再発見・再評価 |
|
田川新一朗 |
|
地域文化遺産の再発見・再評価と保存・活用システム
研究課題石造鳥居の保存状態調査および保存修復技術 |
|
宮本長二郎 |
|
地域文化遺産の再発見・再評価と保存・活用システム
研究課題山形盆地に遺る石造鳥居群の建築学的調査 |
|
長谷川文雄 |
|
地域文化遺産の映像による保存・活用システム
研究課題地域文化遺産の映像デジタルアーカイブ創製 |
|
 |