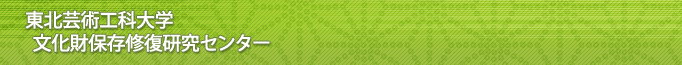 |
|||||
|
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
3つのプロジェクトはいくつかの共通する目的をもっている。これらの目的は、本プロジェクトの推進において各課題を通じて太く貫くとともに、大きな目標ともなっている。 |
||||||||||||
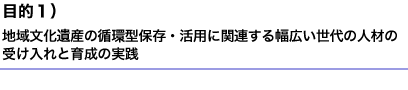 国内の若手研究者(保存修復家や考古学者、PD・RA等)の受け入れ・育成、アジア諸地域の若手研究者(保存修復家・考古学者)の受け入れ・育成、地方公共団体実務家(文化財関係者)の受け入れ・育成、姉妹校の京都造形芸術大学・大学院との連携による学部・大学院生の教育実践、地域における保存修復専門家(高度専門職業人)の受け入れ・リカレント教育、NPOとの連携による人材育成、国内外の専門機関との連携による若手研究者のインターンシップ教育、学校教育との連携による児童・生徒への文化遺産の啓蒙教育、高齢者を対象とした文化遺産解説ボランティアの育成などを実践していく。 国内の若手研究者(保存修復家や考古学者、PD・RA等)の受け入れ・育成、アジア諸地域の若手研究者(保存修復家・考古学者)の受け入れ・育成、地方公共団体実務家(文化財関係者)の受け入れ・育成、姉妹校の京都造形芸術大学・大学院との連携による学部・大学院生の教育実践、地域における保存修復専門家(高度専門職業人)の受け入れ・リカレント教育、NPOとの連携による人材育成、国内外の専門機関との連携による若手研究者のインターンシップ教育、学校教育との連携による児童・生徒への文化遺産の啓蒙教育、高齢者を対象とした文化遺産解説ボランティアの育成などを実践していく。 |
 |
||||
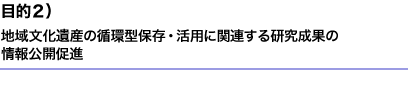 文化遺産の持続的保存・継承には、地域市民が関心をもつことが絶対条件である。そのためには、公開による損傷・劣化のリスクを考慮しつつ、文化遺産を積極的に公開しなくてはならない。保存修復作業・埋蔵文化財発掘調査の現場公開、研究成果に関連した展覧会開催、プロジェクト意義や目的を説く講演会や研究成果シンポジウムの開催、研究報告書・紀要の定期的発行、インターネット・ホームページの充実、文化遺産と地域をつなぐ芸術祭の実施、写真や映像を使った地域文化遺産の紹介、などにより市民と文化遺産を接近させるとともに文化遺産の循環型保存・活用についての一層の理解を図っていく。また、3Dやバーチャル・リアリティによる高度情報化(IT)、ビデオ等による文化遺産のデジタルアーカイブ化により集積した情報を多くの市民が文化遺産に親しめ、商業にも活用できる形に加工し公開を促進する。 文化遺産の持続的保存・継承には、地域市民が関心をもつことが絶対条件である。そのためには、公開による損傷・劣化のリスクを考慮しつつ、文化遺産を積極的に公開しなくてはならない。保存修復作業・埋蔵文化財発掘調査の現場公開、研究成果に関連した展覧会開催、プロジェクト意義や目的を説く講演会や研究成果シンポジウムの開催、研究報告書・紀要の定期的発行、インターネット・ホームページの充実、文化遺産と地域をつなぐ芸術祭の実施、写真や映像を使った地域文化遺産の紹介、などにより市民と文化遺産を接近させるとともに文化遺産の循環型保存・活用についての一層の理解を図っていく。また、3Dやバーチャル・リアリティによる高度情報化(IT)、ビデオ等による文化遺産のデジタルアーカイブ化により集積した情報を多くの市民が文化遺産に親しめ、商業にも活用できる形に加工し公開を促進する。 |
 |
||||
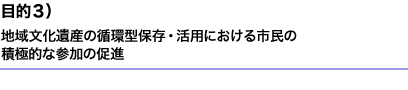 市民にとって、地域において守られてきた文化遺産は、地域の歴史文化を語り祖先の優れた知恵や美意識を甦らせる貴重な共有の財産である。文化遺産の展示や情報の公開により、地域にアイデンティティと責任をもち愛情を注げる市民世代各層(子供から高齢者)のへ文化遺産に対する理解を促し、保存・活用活動への参加を一層活性化する必要がある。文化遺産の保存や活用のあり方に高度の専門性や地域拠点としての機能をもった当センターが地方公共団体や文化財収蔵施設、地域コミュニティとの密接な連携を図ることで地域市民へ様々な働きかけをしていく。文化遺産を中心とした保存・活用を共に考える会の設置など、市民の組織化もその一つの方法であろう。[大学−行政−市民]が一体となった活動を模索したい。市民が参加できる「芸術祭」は、循環型保存・活用にとって文化遺産と市民を近接する力となろう。また、本学が現在進めている「美術館大学構想」(=キャンパスを丸ごと美術館とみなし、市民への芸術作品・歴史資料の公開・展示を常態化するとともに創造活動を支援し活力を与える場の提供)とも大きく関係し、市民が文化遺産と接し、参加する機会を提供する。 市民にとって、地域において守られてきた文化遺産は、地域の歴史文化を語り祖先の優れた知恵や美意識を甦らせる貴重な共有の財産である。文化遺産の展示や情報の公開により、地域にアイデンティティと責任をもち愛情を注げる市民世代各層(子供から高齢者)のへ文化遺産に対する理解を促し、保存・活用活動への参加を一層活性化する必要がある。文化遺産の保存や活用のあり方に高度の専門性や地域拠点としての機能をもった当センターが地方公共団体や文化財収蔵施設、地域コミュニティとの密接な連携を図ることで地域市民へ様々な働きかけをしていく。文化遺産を中心とした保存・活用を共に考える会の設置など、市民の組織化もその一つの方法であろう。[大学−行政−市民]が一体となった活動を模索したい。市民が参加できる「芸術祭」は、循環型保存・活用にとって文化遺産と市民を近接する力となろう。また、本学が現在進めている「美術館大学構想」(=キャンパスを丸ごと美術館とみなし、市民への芸術作品・歴史資料の公開・展示を常態化するとともに創造活動を支援し活力を与える場の提供)とも大きく関係し、市民が文化遺産と接し、参加する機会を提供する。 |
 |
||||
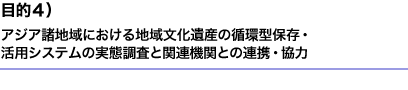 アジア諸地域には、わが国の文化財と共通する材質や構造をもった文化財を継承してきた国や地域が少なくない。具体的には、紙や絹、木材を支持体とする書画、漆喰などを支持体とする壁画、遺跡から出土する金属や木材、漆等による埋蔵文化財、石材等を主体とする記念物などが挙げられる。これらの保存・活用に当たっては、アジア各国・各地域における特徴的な実践から学ぶとともに、保存修復の理念や技術を相互に研究することも重要である。すでに本学・東北文化研究センターでは、「オープン・リサーチ・センター整備事業」の支援を受けて、東アジア諸地域での民俗文化に関わる研究を展開している。本プロジェクトもこの研究との連携を強化していく。また台湾では1999年に大地震に見舞われ、韓国では最近水害を受けたように、近隣諸国では文化遺産への防災・被災対策は大きな課題となっている。各国・各地域における文化遺産・考古学機関との交流を促進し、連携・協力体制を構築する。 アジア諸地域には、わが国の文化財と共通する材質や構造をもった文化財を継承してきた国や地域が少なくない。具体的には、紙や絹、木材を支持体とする書画、漆喰などを支持体とする壁画、遺跡から出土する金属や木材、漆等による埋蔵文化財、石材等を主体とする記念物などが挙げられる。これらの保存・活用に当たっては、アジア各国・各地域における特徴的な実践から学ぶとともに、保存修復の理念や技術を相互に研究することも重要である。すでに本学・東北文化研究センターでは、「オープン・リサーチ・センター整備事業」の支援を受けて、東アジア諸地域での民俗文化に関わる研究を展開している。本プロジェクトもこの研究との連携を強化していく。また台湾では1999年に大地震に見舞われ、韓国では最近水害を受けたように、近隣諸国では文化遺産への防災・被災対策は大きな課題となっている。各国・各地域における文化遺産・考古学機関との交流を促進し、連携・協力体制を構築する。 |
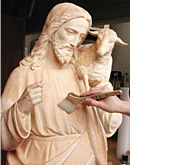 |
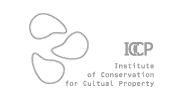 |
|||