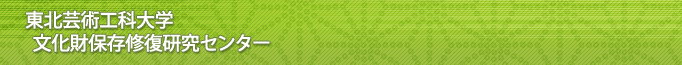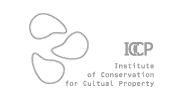|
2008年11月28日
本写真展は、平成17~21年度文部科学省私立大学オープンリサーチセンター整備事業の助成を受けて
開催されます。
2008年度企画写真展
「人・地域・文化をつなぐ街道文化遺産の光」
21世紀型社会を目指すにあたって、本来的な「心の豊かさ」は最重要なテーマとなっている。
近代科学文明の進歩は輝かしいばかりだが、決してそれ自体が豊かさの象徴にはなるまい。人とのつながりを失い、産業経済社会の一部品として、大量生産と消費の無機的な関係を生きる現代人は果たして豊かなのか。社会と個人の幸せへのベクトルが重な合い、「人」と「地域」と「文化」がつながり、相互が心の底から響きあってこそ真の豊かさと言えるのではなかろうか。怒涛の近・現代を全力で突き進んできた我々の前道に、「本来的な心の豊かさ」が抜け落ちている。一体それは何故か。
高度経済成長に裏付けられた「ものの豊かさ」も、資源のリミット時計が動き出した昨今においては幻いとなりつつある。現に、人口減少、過疎化、財源委縮、格差社会、一方向のグローバル化、環境と金融危機など様々な影響により、地域の現実は益々厳しさを増している。この現状を冷静に受け止めながら、地域の新しい活路を真剣に考えなければならないのである。地域と地域との境界の垣根を越え、「人」と「地域」と「文化」がつながる、芸術・文化の広域連携の取り組みが今強く求められている!
2008年10月1日、「観光庁」がはじめて国の正式な機関として発足した。地球規模で年間数億の人々が飛び回る時代とあって、「観光立国」の発想は大いに評価すべきるものである。「観光」とは、日常から離れて異なる文化に触れる「旅」とも言える。旅の御利益は、旅する人自身が豊かになれると同時に、旅を受け入れる側も豊かさを分かち合える。さらには、旅先での出来事が刺激となり、新たな文化形成につながる。旅とは、内なる「光を求める」行為であり、抜け落ちた「心の豊かさ」を回復するための最たる「文化的な行為」に他ならない。もし、人類が旅をしなかったら、文明そのものが変わっていたかも知れない。
かつて、出羽三山を目指した多くの人々は、山形を含めて関東から東北まで広域に形成された講中檀那衆であった。彼らは聖山として拝められる出羽三山詣でという旅を通して、生きることの喜びと命あるものの運命を感じとって、心豊かな精神文化を享受していた。人間味あふれる、生き生きとしたエネルギーに満ちた街道沿いの生活臭。社会的な通念、宗教のカテゴリーさえを越えて旅先で出会った人々とのつながり。大自然に抱かれて透けて見える人間本来の無垢な姿。その道に心から求められる「光」があったに違いない。大規模の社寺や、荘厳な神仏像は人間による信仰の証しだが、それらをはるかに超えて存在する「光」。出羽三山の奥の院に代表されるように、「何もない所が故に」溢れ出る「光」が街道に差し込んでいたのである。その「光を観て、触れる」ために、大勢の人々が草鞋を履いて街道を練り歩き、ひたすら湯殿を目指していた。その行列のなかには松尾芭蕉、菅江真澄、高山彦九郎、斉藤茂吉、丸山薫、真壁仁、井上靖、森敦、藤沢周平・・・そして、岡本太郎が居た!
多くの人々が求めていた「光」とは一体何だったのだろうか。今もう一度、この街道空間(=山形)にその「光」を発現できないだろうか。現代によみがえる六十里越街道の姿に、新しい「光」をもとめる21世紀型社会の未来像を重ねてみては如何だろうか。本企画展では、明治時代を境に眠りに入った六十里越街道をとりあげ、「街道文化遺産」の意義と魅力、そしてその可能性に光をあてる。一方で、山形の文化遺産がもつ空間的な価値について再認識を行い、時代を「切り開く」文化遺産の可能性と、社会的なビジョンの共有をはかっていく。
|
■ 場所
|
|
|
霞城セントラル23階展示室
|
|
■ 日程
|
|
|
2008年11月15日(土)~2009年1月18(日)
展示時間10:00~16:00(月曜日休館)
|
|
■ 展示内容
|
|
|
展示される主な写真は、東北芸術工科大学、東北公益文科大学の学生たちと一般市民が、全街道区間を歩いた記録(2008年9月22日~9月27日)を中心に、山形を代表する街道沿いの歴史遺産+自然遺産+生活文化遺産をご紹介する。
写真パネル:約80点+拓本資料5点
|
|
■ 関連企画その2
|
|
ギャーラリー・トーク
|
|
|
2008年12月20日(土)13:30-16:00
霞城セントラル23階展示室+会議室
参加費:無料・申込なし
「六十里越街道の全行程を歩く会」の参加者たちと一般市民を招待し、歩く会を振り返るとともに、今後に向けてのネットワークづくりをはかる。
|
|
|
【問い合わせ】
東北芸術工科大学 文化財保存修復研究センター
023-627-2204
|
|