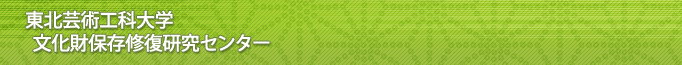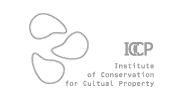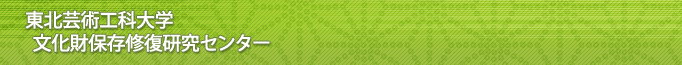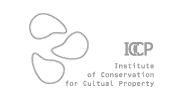|
2007年12月26日
『山形文化遺産防災ネットワーク』発足記念シンポジウム
第4回 人と文化遺産保存継承ミーティング
主催:東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター
共催:山形県立博物館
後援:山形県教育委員会、朝日町教育委員会、大江町教育委員会、尾花沢市教育委員会、
長井市教育委員会、遊佐町教育委員会、致道博物館、山形県博物館連絡協議会(申請中を含む)
|
■ 趣旨
|
|
|
1995年の阪神淡路大震災以来多くの地震災害が列島を襲い、わが国を始め地球上の多くの地域で地震の活動期に入っているとの見方が一般的です。幾多の地震災害だけでなく、地球温暖化の影響とも指摘される自然災害が続発しているのも頭痛の種です。「災害の少ない」と言われる山形県も盆地各地に活断層が確認され、大規模な震災の可能性が指摘されています。また明治における庄内地方の地震では数百人が落命し、昭和の羽越水害でも甚大な被害をもたらしたことを史実が語っております。いずれ山形でも、大規模な自然災害の発生と被災は避けられないと考えるべきです。
災害が来てから考え対応するのではなく、来るべき災害に備え地域の文化遺産を守るため、地域における人々の緩やかな連携(ネットワーク)活動を日常的に進めたいと考えました。市民は、文化財の担当者も、本ネットワークの参加者も押しなべて被災者になります。その上で瞬時に文化財保護に力を注ぐことは極めて難しいことですし、緊急時は文化財よりも地域の人命や財産、ライフラインを守る取り組みこそ最重要です。地域文化遺産の救済活動にいち早く対応したくても地元の人が動けない、わかっているけど手が出せない、そんなときに手足となって活動を支援する人的なネットワークを県内で立ち上げたいと考えています。また本ネットワークでは日常においても、指定・未指定文化財の所在地調査やパトロール、地域の歴史家との協働による文化遺産の悉皆調査など有事に備える活動を展開していきます。さらに隣県や他地域で活動する同様のネットワークと広域的な連携も進めるべきと考えています。
以上のような内容について有志の中で話を進めていくうちに賛同者が増え、またこれまで山形の文化遺産保護に尽力し牽引されてこられた先達の方々にもご理解をいただき、この度「山形文化遺産防災ネットワーク」を設立する運びとなりました。これを記念し、シンポジウムを開催いたします。趣旨にご賛同いただける方々、ご興味のある方々はぜひご参集ください。
|
|
■ 日時
|
|
|
2008年01月25日(金)13:00~16:40
|
|
■ 会場
|
|
|
山形県立博物館 講堂 : 山形県山形市霞城町1-8(霞城公園内)
|
|
■ スケジュールと内容
|
|
|
総合司会:手代木美穂(東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター)
13:00-13:05 開会の挨拶
松田泰典(文化財保存修復研究センター長)
13:05-14:05 招待講演「地域の文化遺産を千年後まで残そう」
平川新(東北大学東北アジア研究センター教授・
NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク理事長)
14:05-15:15 座談会(1)
「山形における文化遺産の保護・継承活動~これまでとこれから~」
川崎利夫(元うきたむ風土記の丘館長)
横山昭男(山形大学名誉教授)
大友義助(新庄民話の会名誉会長)
渋谷孝雄(山形県文化財保護室)
モデレータ:松田泰典
15:15-15:30 休憩
15:30-16:30 座談会(2)
「山形文化遺産防災ネットワーク~つながる活動経緯とその内容」
小林貴宏(うきたむ考古の会事務局)
岡崎国宏(朝日町教育委員会)
友野毅(遊佐町教育委員会)
栗原伸一郎(東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター)
モデレータ:手代木美穂
16:30-16:35 「山形文化遺産防災ネットワーク発足宣言」朗読
16:35-16:40 閉会の挨拶
阿部寛(山形県立博物館館長)
16:40-16:40 閉会
|
|
■ 参加者
|
|
|
ネットワーク活動の賛同者および文化遺産の保存継承や防災活動に興味のある方々
|
|
■ 参加費
|
|
|
無料
|
本シンポジウムは東北芸術工科大学文化財保存修復研究センターが選定を受けている平成17-21年度文部科学省私立大学研究高度化推進事業「オープン・リサーチ・センター整備事業」の一環として開催されます。
|
|
|
【申込み・問い合わせ】
東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター
023-627-2204
|
|