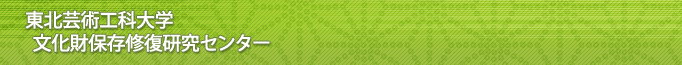 |
|||||
|
|
|||||
そして、今何故石造文化遺産の保護活動を考えなければならないのか。 近年の保存工学の研究成果をもとに石造文化遺産の保護のあり方を探る―
主催:東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター
後援:山形県教育委員会、山形市教育委員会、山形新聞社
|
|||||||||||||||||||||
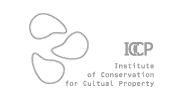 |
|||
|
|
|||
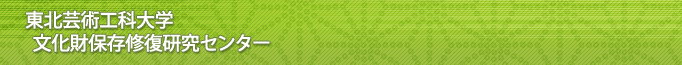 |
|||||
|
|
|||||
そして、今何故石造文化遺産の保護活動を考えなければならないのか。 近年の保存工学の研究成果をもとに石造文化遺産の保護のあり方を探る―
主催:東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター
後援:山形県教育委員会、山形市教育委員会、山形新聞社
|
|||||||||||||||||||||
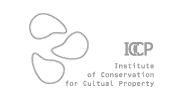 |
|||
|
|
|||